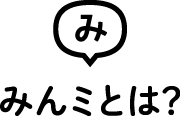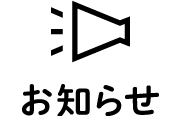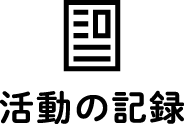【活動紹介】当事者コーディネーターとの協働〜横浜市民ギャラリー〜
- 報告レポート
2024.03.08(金)
みんなでミュージアム(以下、みんミ)は、障害のある当事者コーディネーターを対象とした実践や研修に取り組んでいます。この度、横浜市民ギャラリーで開催された大人のためのアトリエ講座「言葉と遊ぶ、言葉と出会う」を2名のコーディネーターが体験し、気づいたこと、感じたことをフィードバックする研修の機会を設けました。なお今回は、視覚に障害のあるコーディネーターが、ワークショップに参加する際に寄り添う立場として、2名のパートナーが参加をともにしています。
当日の詳しいレポートを、みんミのパートナーとしても活動する井上幸子さんに執筆いただきました。
視覚に障害のある人とともに学び楽しむワークショップのために
1月14日(日)のよく晴れたお昼に、私たちは視覚に障害のある佐々木さんと井戸本さんを交えて桜木町の駅で待ち合わせをした。この日は、言葉にまつわるワークショップに、佐々木さんと井戸本さんはコーディネーター、私はサポーター(※)という立場で参加した。その前に私たちメンバーはランチをともにして軽い自己紹介や雑談を交わし、緊張感も解れたところで会場へ向かうことにした。
※今回は主に、当日の様子を記録してレポートにまとめるサポート。
ワークショップの参加者は20代から60代と幅広く、ほとんどは女性だった。参加者たちには目の見えない人が参加しているという情報があらかじめ伝わっている様子ではなかったが、講師や他の参加者の方々によるさり気ない優しい気遣いのなかで、ごく自然に時間は過ぎていった。私自身、サポーターという任務がありつつも、皆さんと一緒に楽しみながら参加していた。
当日のワークショップの様子
ワークショップは、まず、およそ30分間のイントロダクションに、与えられた言葉の頭文字から詩をつくるという内容からはじまった。「ふじさわ」「あのまち」から始まるそれぞれの作品はどれも個性を感じられるものだった。人の詩を入れ替えてみては、今考えた景色とは違うものが自動的にできあがるという遊びを楽しんだ。それぞれの作品を鑑賞しながら笑いあい、温かい雰囲気が流れていた。
そしていよいよ本題は、予め用意されていた3つの横浜市民ギャラリーの所蔵作品の中から気になるものをひとつ選び、3チームに分かれて、選んだ作品から得られたインスピレーションから「連詩(れんし)(※)」をつくるというものだった。
※最初の詩に対して、その情景から次の詩を想像する文芸
まずは3枚の作品から気になる1枚を選んでチームに分かれた。チームのなかで、選んだ作品の気になる点を共有した。目の見える人たちは視覚的な情報をもとに選んだものが多かったが、私が参加したチームの佐々木さんは「宮沢賢治が好きなのと、消去法でこの絵を選びました。」と選んだ動機を発表した。
そのあと、美術館のエデュケーターから、それぞれの作品の詳しい解説があり、作者の経歴や世界観、制作スタイルなど目の見えない人にも分かりやすい説明がなされた。チームのなかでも、絵から得られるインスピレーションやイメージを、言葉を通してより詳しく参加者と共有した。
連詩をはじめる前に休憩時間があった。その休憩時間に、それぞれ壁に掲示された作品見本を改めて観察する。私は佐々木さんの手を取り、そのアウトラインをなぞりながら「どんな感じ?」「そこは何色ですか?」という佐々木さんの質問に答えながら身体的に再び作品の解説をした。
連詩のはじまりは、先生が予め用意をしてくれた1行目からスタートした。ジャンケンで負けた人から時計回りで続いていく。躍動感あるはじまりから、どんどん盛り上がり、あるとき突然止まり、そして静かにはじまっては、また動き出す。そしてあと戻りをしてみては、きちんと着地するというような、運動を繰り返しながらも展開されてく。各チームによって、メンバーやそれぞれが織り成す言葉のコラージュから世界観がきちんと確立されていたのが面白かった。その場、そのタイミングで出会ったメンバーと言葉などによる偶然性を楽しみつつ、みんなでひとつの作品をつくり上げるという満足感の感じられる充実した時間だった。終始、笑いと驚きに溢れたワークショップだった。

休憩時間の様子。壁に掲示された作品のレプリカに手で触れながら、改めて身体的に観察する。
視覚に障害のある参加者の立場で思うこと
ワークショップを終えて、視覚に障害のある参加者の立場から、佐々木さんと井戸本さんに参加の感想などをお聞きした。
・絵をみることからスタートする内容に、初めは「置いていかれないか」という不安はあった。けれど、選ばれた作品が抽象的な作品だったため、参加者がそれぞれ感じたことから進めていくかたちで参加しやすかった。そういう意味では、見える/見えないに対する隔たりを感じることはなかった。
・ワークショップのなかでは、言葉による説明や声掛けも多く、参加のしにくさを感じることはなかった。
・グループ内に参加していたパートナーが、ごく自然に参加者との間に溶け込んでいて、ワークショップを楽しみやすかった。
・目の見えない人が参加するという情報が、あらかじめ伝わっていなかった点について、人によっては事前に知りたいと思う人がいたかもしれないが、前知識がなかったからこそ、その場の自然なコミュニケーションのなかで参加ができたように感じた。
・ワークショップのなかで、作品を選択する時間、あるいはその場所がもう少しほしかった。例えば、休憩時間における工夫として、「目の見える人が作品を観察できるスペース」と、「目の見えない人が作品を身体的に理解できるスペース」と分かれていたら良かったかもしれない。今回は、目の見えない人が作品をより理解するために、時間や場所を占めてしまうかたちとなってしまった。
・障害のある参加者として、ハードルを高く思われないためにも、特別な対応を求め過ぎてはいけない。そして支援する側としてもその場の雰囲気を壊すほどの手厚さは必要ないと思う。

ワークショップの様子。
支援の在り方として思うこと
ワークショップ全体を通して、さまざまな角度から感想があげられた。
題材が抽象的な要素がある作品であったことは視覚障害のある当事者にとっては比較的参加がしやすかったことにくわえて、自由な発想をあと押しするのに詩との相性もとても良いものだったと思う。
視覚に障害のある人とともに学び、楽しむために全体を通して改めて思うことは、目が見える人にとっての当たり前を、どこまで目が見えない人にとっての当たり前に目線をずらして考えることができるか、ということだ。それは一人一人が違う個性を持ち合わせた人間であるように、障害の有無に関わらず、お互いを理解するという点でも同じようなことが言えるのではないかと思った。障害の程度によって必要とされる支援の内容も異なるけれど、それらは前提として大事な観点だと改めて認識した。今回、同じチームでご一緒させていただいた佐々木さんは、必要なときに質問をして頼ってくれるという自主的な姿勢があったため、私自身も安心してワークショップに溶け込み、楽しむことができたように思える。必ずしも積極的で自主性の高い当事者が参加するとは限らないけれど、支援する側される側のそれぞれが、できるだけ対等な目線で、一緒に楽しむというスタンスがちょうど良いのかなと思った。そしてそれを実現するためには、障害のある当事者と支える人という関係性はもとより、それらを取り巻く全ての関係者の皆さんによる総合的な「さり気ない優しい力」によって生みだされる心地良さであるのかも知れないと思った。
文:井上幸子